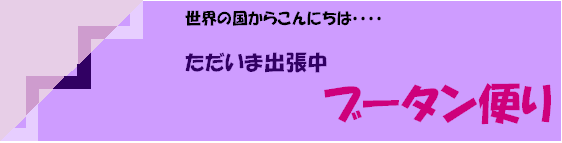
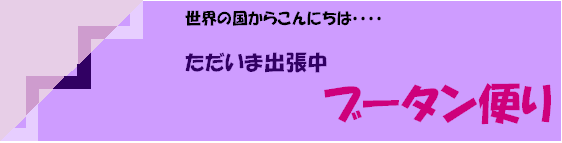
| 31.幸運のお守り(後編)
「セルドン、おまえはまだ15才だ。でも真実を受け止めるには十分な歳だろう。それに、いまこの時期に話すしかないんだよ」
少女の叔父が頬を伝う涙とともにそう話すあいだ、叔母は少女の傍らに座り彼女の手を握ってすすり泣いていた。
「大丈夫よ、受け止められるわ、おとうさん。この何年間もおとうさんおかあさんが私のことでずっと心を痛めてきたことがわかったのだもの。大丈夫よ、おとうさん。すべてを話して」
セルドンは真っ赤にはらした目から溢れ出るしょっぱい涙で服を濡らしはじめながら、懇願するように言った。
「もっと後に話すこともできたんだよ。でも、いま、話さなければならなくなった。なぜなら・・」
「どうしてなの? いったい何が起きたっていうのおとうさん・・」
「亡くなったテンジンはおまえの実の父親なんだよ、セルドン。このことはおまえにはずっと隠していたことだがね」
デンドゥップは努めてさらりともう一つの真実を語った。
「えっ、このあいだシャムリンで息子さんの死に直面してショックから亡くなった、あの人が?」
セルドンは驚きの表情を顔全体に顕して聞き返した。
「そうだ。聞くところでは、彼は自分の息子がまたもや毒で死んだということを知ったショックで亡くなくなったということだ」
デンドゥップは遠くを見つめながら言った。
「おお、神様! なんてことなの!」
セルドンはあまりにも衝撃的なもう一つの真実を聞き、崩れ落ちた。
「明日はテンジンの死後21日目の法要が行われる。だから、おまえが実の父親にお別れとお祈りを捧げる最後の機会になると思ってな・・」、 と叔父は話した。
翌朝早く、セルドンは養父母とともに彼女の実の父親とその家族の最後の法要に出かけた。しかし、彼らが法要の行われている寺院に入ろうとしたちょうどそのとき、ひとりの老女がセルドンに向かって怒りに声を震わせながら叫んだ。
「この、毒もりめが! おまえの母親はわしの息子を殺し、嫁を殺し、孫達全部を殺したんだ! おまえはここへ残っているわしらを殺しにやってきたのか!」
「ばあさん、私のこの娘は実の父親に最後のお別れと祈りを捧げに来たんだ。あんたの家族がひどいつらい思いをしたのはわかる、私も同情する。でも、どうか自分を抑えてくれ。私の娘に 公衆の面前でこんな風に屈辱を与えないでくれ。」
「おまえの娘だって? おまえがこの娘を自分の子だと言って、この魔女の運命を変えられるとでも思ってるのかい?。いずれ、この娘も母親と似たり寄ったりのものになるのさ。こいつは毒もり以外のなにものでもないんだからね。そうさ、おまえもわしも、 そしてみんなが知ってるようにね!」
老婆は周囲の注意を一点に引きつけるように叫び続けた。
「やめろ、そんなばかげたことを言うのは!」
デンドゥップは右手を蛮刀の柄にやり、怒りに震えながら老婆に警告した。 セルドンと妻は必死でデンドゥップを掴み、寺院を離れようと懇願した。 そして彼らが歩き去ろうとするとき、老婆は彼らが視界から消え去るまで、セルドンに向かって罵声を浴びせ、ツバを吐き続けた。あわれなセルドンは、家に帰るまでずっと、泣くことで彼女に浴びせかけられた屈辱を拭い去ろうとしていたかのようだった。
「すべて、私が悪かった、セルドン。21日法要に行くなどということを私が言い出さなければこんなことには・・」
「おとうさんが悪いんじゃないわ。私はすくなくともきちんと礼を尽くそうとできたことがうれしい・・・」、と言いながら彼女はまた崩れ落ちるように座り込んだ。
その晩、他の家族が寝静まった頃、セルドンは養父母のところにやってきて、低く呟くように言った。
「おとうさん、おかあさん。私、決心したわ」
二人は不安げにお互いの顔をちらりと見合わせてからセルドンを見た。 永遠続くと思われるよう長い沈黙の後、デンドゥップは震える両手でセルドンの手を握りしめ、しわがれた声で彼女の決心を尋ねた。
「いままでずっと、苦々しい思いをずっと黙って呑み込もうとしてきたわ。人はいつも私を避けようとしたし、遊び仲間は私のことを『毒もり』って何度も何度もはやし立てたわ。そして、今日・・・。」
彼女は父親の肩にもたれかかるようにしてすすり泣いた。
「セルドン、そんなふうに考えちゃいけないよ。おまえだって、みんなが言っていることはデタラメだって知ってるだろう? それに・・・・」、妻はなんとか彼女を慰めようとした。
「おかあさん、もうたくさんなの。私はいずれにしても、生きてる限り毒もりか毒もりの娘なのよ」
「そのことがどんなにかおまえを傷つけているか、わかるよセルドン。だがな、これはどうしようもないことなんだよ。」、デンドゥップは言った。
「だから私はこの村を離れ、家族とも別れることを決心したの。私のことを誰も知らない遠くの土地へ行って、新しい生活を始めるわ。」
セルドンは、養父母のことばなど全く聞いていないかのように宣言した。
「でも、おまえはたった15の娘じゃないか。家を出ることなんてできるはずがないじゃないか!」、デンドゥップは低く叫んだ。
「だめよ!セルドン。そんなことは言わないで。私たちを置いていくなんて。どうして私たちを置いていくなんてことができるの? どんなにかおまえのことを思って今日までやってきたか・・。」、養母は ためらうことなく感情をセルドンにぶつけた。
「お願いよ、わかって、おかあさん。家族みんなのことを愛し尊敬しているの。でも、私はそうしなきゃならないのよ。それしかないの。」、セルドンはそう言いきった。
「だって、おまえはたったの15才なんだよ。どうしておまえをそんな遠くに一人でやることなんかできるものか。なんてこった。真実を語ったあと、娘自身にそのあとの生き方を決めさせるなんていう約束を、この私が姉さんと さえしなければ、こんなことにはならなかったのに。」
デンドゥップは悔やんだ。
「でも、そうしないと私、もう一生幸せに暮らす事なんてできないのかも知れないわ」 セルドンは言った。
「もし、本当におまえが行かなければならないのなら、俺がついて行ってやる!」
部屋の薄暗い隅っこから聞こえたその声に、3人はぎょっとした。それは19才になるセルドンの従兄のワンチュクだった。
「そんな暗闇でお化けのように何を突っ立ってるんだ。こっちへ来い」、デンドゥップがワンチュクを叱った。
「そっちこそ、夜中に3人だけでそんな大切なことを話すなんてどういうことだい。3人とも寝ないからなんかおかしいとは思ってたけどさ・・」、と話ながらワンチュクはセルドンの隣に座った。3人はなんと答えていいかわからなかった。
「どんな気持ちで俺をおいて逃げていこうと思ったんだ、え? おまえを罵倒した村の子供達を殴りとばしてきたのは、この俺じゃなかったのか? それに、俺が本当の弟妹以上におまえを愛さなかったとでも思ってるのか? どうなんだ?」
ワンチュクは、こぼれ落ちて口に入った涙の後を引くしょっぱさを感じながら、セルドンの肩を軽くこづいて、声にならない声で言った。そして泣きじゃくるセルドンに抱きつかれながら、ワンチュクはさらに言った。
「もしおまえがどうしても行きたいというのなら、俺が地獄まででもおまえについていってやる!」
4人は闇の静けさの中でしばし泣きつづけた。そして、その沈黙を破ってデンドゥップが意を決したように言った。
「よし、わかった。ワンチュクがセルドンについていくと言うのなら、身の安全についてはそんなに心配はない。明日、おまえ達の出発の用意をしよう。そして、明後日の朝、3番鳥が鳴いたら出かけるんだ。4頭のポニーに必要なものすべてを積んでやるからな。でもな、絶対にこのことは秘密だぞ、おまえ達の弟妹たちにもな。」
と、デンドゥップは一気に話した。そしてしばらくの沈黙の後、抑えきれない嗚咽を漏らしながら、さらに続けた。
「でもな、セルドン。頼むから約束してくれ! 私たちが老いて死ぬ前には、一度でいいから必ず会いに来てくれよ。そして、ワンチュク。おまえはしっかりセルドンの面倒をみてやるんだぞ。なにかセルドンの身に危険が起きたときには、たとえ自分の命を賭してでも妹を守るんだぞ!」
「わかった、約束するよ」、2人はほぼ同時に答えた。
ラモはけだるそうに歌いながら、背負ったかごに乾燥した松かさを投げ入れていた。彼女の物憂げで心にしみわたるような歌声は、カッコーさえも恥ずかしさのあまり隠れてしまうほどに美しいものだった。彼女の歌声は松林を抜け、断崖に反響して谷に響き渡った。
「あと一杯集めれば十分だわ」
彼女は自身に言い聞かせるように呟き、松かさの一杯詰まったかごを背負って家に向かって歩いていった。彼女はこの2日間ずっと松かさを集めていたのだった。彼女は、穀物を貯蔵するための家の床下の空間に、すでにほぼ一杯の松かさを集めていた。彼女はさらに、屋根裏部屋にも一杯の干し草と、松かさを集めていたのである。
「なんか、今年の冬はずいぶん寒くなるみたいなのよ・・」
ラモは母親に「なんでそんなに松かさを集めるのか」と訊かれた時にそう答えた。
「だっておまえ、一年以上も足りるような十分な薪があるじゃないか」、老婆は言った。
「備えあれば憂いなしよ」、彼女はそういって母親を納得させようとした。
「でもね、おまえ、屋根裏だけじゃなくて床下まで置いておくのは危険だよ。」
「かあさん、火事でも恐れてるの?」、娘は母親をからかうように言った。
「どうしてよ、かあさん。あの椀がかあさんを守ってくれるじゃない!」
「わかったよ、好きにおし、ラモ」、老婆はそれ以上議論するのをやめた。
そのとき、ラモは2日前に弟のデンドゥップが訪ねてきたときのことを思いだしていた。彼は遠く離れたところから彼女を呼んだのだった。
「ラモ姉さん、僕は15年前に交わした約束を果たしたからね。」
ラモが駆け寄っていったとき、デンドゥップは最初にそう言った。そして、彼はラモにすべての出来事を話して聞かせた。実父の法要に出かけたときにその母親である自分の祖母にセルドンがひどく罵られ追い返されたこと、そして、5日前にワンチュクとともにセルドンが行く宛も知れない旅に出たことを・・。
「セルドンが正しい判断をして、姉さんもしあわせだろ?」、デンドゥップはラモの家を後にする前にそう言った。
それは、ラモにとって生涯の中で聞かされた最もよい知らせだった。そして彼女は生まれて初めてうれし涙を流したのであった。
「弟よ、どんなにおまえに感謝していることか。でもね、私もいつの日かセルドンが誇りに思ってくれるようなことをしなくちゃね。」
「ねえさん、僕は自分の約束、そしてセルドンの養父としての役目をしっかり果たしたからね。これからはずっといい人でいておくれよ。」
デンドゥップはそう姉にそう忠告し歩き去った。
その晩、ラモが仏間に入ったとき、母親はコインの入った椀を両手で抱えじっと立ちすくみ、その椀を見つめていた。
「かあさん、どうかしたの?」、ラモは何気なく訊いた。
「この音がおまえ、聞こえないのかい? ほら、ごらん。コインが動いてるじゃないか!」 老婆はおびえてその椀をラモの顔の前に突きだして言った。
「いいえ、かあさん」
ラモは、さらに何気なく母親をからかうかのように言った。母親の見、そして聞いたものを同じように確認しながら・・・。
実際、ラモはデンドゥップが彼女を訪ねた日の夜から椀の中のコインがチャリン、チャリンと鳴りはじめたことに、そしてそれがなぜかに気づいていた。
「これは、悪いきざしだよ」、と老婆は喘ぐように言った。
「やめて、かあさん、くだらない! もう、こんな馬鹿げた椀にはほとほと嫌気がさしてるんだから!」
ラモはそう叫びながら椀を母親から奪い取って部屋の隅に投げつけ、ものすごい勢いで部屋から出ていった。 だが、台所に座っている間、ラモは隣の部屋のコインの音がより一層大きくなっていくのに気がついていた。
その晩、母親が仏間で寝入った頃、ラモは台所で無心に呪文を唱えていた。そして真夜中近く、彼女は外から仏間の錠をしっかりとかけた。それから仏間の隣の彼女の部屋の床一面に、ありったけの布きれと布団を音を立てないように広げた。そして彼女は台所に行き松明を両手に持ち、そのうちの一本に火をつけて床下の貯蔵庫に入っていった。彼女は注意深く、松明の束を乾燥した松かさの山の下に置いた。火が部屋に回り始めたとき、ラモはもう一本の松明に火をつけ、今度は屋根裏部屋に急いで駆け上がり、そこで火を放った。
その後、今度は下に降りて台所の外に置いてあった、今日集めたばかりの松かさを持って台所に入り、うしろでしっかりとドアを閉めると、かまどに目がけて松かさの半分を投げつけた。そのあとかまどの薪を取り出して松かさの上におき、火をつけた。そして彼女は自分の部屋に駆け込んでしっかりと扉に鍵をかけたのである。そのころまでに、彼女の部屋は煙で一杯になり、すでに床下からの熱も感じられるまでになっていた。
「ラモ、起きて! 家が燃えてるよ!」、母親が煙に咳き込みながら叫んだ。
「わかってるわ、かあさん。私が火をつけたのよ!」
ラモはそう叫び返しながら、自分の部屋の木箱に積み上げた残りの松かさの山に薪の切れ端で火をつけていた。
「気でも狂ったのかいっ! 早く扉を開けておくれ!」、母親はさらに激しく咳き込みながら、必死に扉を開けようとして叫んだ。さらに、窓のところに駆け寄り、開くはずもない窓を必死に開けようともがいた。
「もう、窓は外から打ち付けてあるのよ、かあさん。だから、開けようなんてもがいて貴重な息を無駄にしないことね!」、ラモは母親が爪で窓をひっかく音を聞きながら大声で叫んだ。
そのころには、屋根はすっかり炎に包まれていた。そして床下からの炎は早くも壁を這い上がり、床も呑み込もうとしていた。母親は仏間の窓や屋根から入り込んできてすべてを呑み込もうとする炎の痛みに悲鳴を上げた。
「ラモ、後生だからぁ、ここから私を出しておくれぇ・・・」、母親は泣き叫んだ。
「叫ぶがいいわ、魔女! あらん限りの力で叫ぶがいい!」、ラモは彼女自身の部屋が炎にすっぽりと呑み込まれ、彼女の着物にも炎が回るなかでそう叫び返した。
「お守りの椀がどうやって救ってくれるのか、よく確かめたらいいわ。あんたもあんたの母親も、私を毒もりにしたんじゃないの! あんたたちは私に何の罪もない人たちをたくさん殺させたのよ! わたしの愛するチェリンまで!」、ラモはさらに叫び続けた。
「今夜、あんたと私、そしてあの忌まわしい椀の呪いを断ち切ってやるの!」
取り憑かれたかのように、ラモはそう宣言した。
そしてまもなく、炎がすっぽりとラモを包み込んだ。
火事は次の朝になってやっと発見された。発見者の牛飼いは急いで隣村の住人に火事のことを知らせた。最初の村人達のグループが現場にたどり着いたときには、すでに家もその住人もなく、わずかな土壁と、真っ赤な焼け残りの山がくすぶっているだけだった。村人達は、憐憫の情と、「これで毒もりの恐怖から解放される」との安堵との混じり合った複雑な思いを抱いて現場を後にした。村人達は、彼らの村と毒もり一家との直接視界を遮る峠にさしかかったとき、家のあった焼け跡を振り返った。朝陽が彼らの背後から、遠くの焼け跡を照らしていた。そして、驚いたことに、その焼け跡の中央部付近で、何かが朝陽を受けて眩いばかりに光っていたのだ。しかし、誰もそれが何であるかを確かめようと、あえて戻ろうとはしなかったし、気にもとめようとしなかった。
そのころ、ずっと離れた遠くの谷で、セルドンとワンチュクは楽しそうに竹の吊り橋を渡っていた。橋の反対側では一人の旅人が、親切にも黒い馬を御し二人をやり過ごすために待っていた。
「若いお二人、どちらまで行かれるのですか?」、旅人は尋ねた。
「私たちの夢の国までですよ、おにいさん」
セルドンがワンチュクの肩にしがみついて橋を渡りながらくすくす笑っているとき、ワンチュクが素早く答えた。
「あなたはどこまで行くんですか、おにいさん」、ワンチュクも尋ねた。
「シャムリンとその近くの村までね」、旅人は答えた。「あなた達はその辺りから来たんじゃないんですか?」
若い二人は顔を見あわせてにっこりと笑い、同時に肩をすぼめ、「聞いたこともないなぁ、そんなところは」、と答えた。
それから、旅人が見守るなか、若い二人は、4頭のポニーを引き連れ、楽しそうに笑いながら谷を登っていき、いつか旅人の視界から消えていった。旅人もまた、その若い二人の微笑み、笑い声が耳にこびりつき心に残って、しばらくは微笑み、そして頷いていた。
その孤独な旅人が彼の目的地に近づいたころ、彼は数日前に焼け落ちたと思われる道ばたの民家の焼け跡にさしかかった。彼はその焼け跡の前に立って、たとえそれが誰の家であったかは知らないにしても、その家族の失ったものの大きさに心を痛め、そしてまたその火事で誰も傷ついていなければいいのだが、と考えていた。
そのとき、焼け跡のなかのある光が彼の目を惹いた。何かに夕陽が当たり、その反射光が直接彼の目に入ってきたのである。そして、彼は取り憑かれたかのように、ゆっくりと、顔の前に手をかざしてその強い反射光を遮りながら、近づいていった。
そして、彼がそのきらびやかな金細工の施された銀の椀にたどり着き、中にびっしりと入った銀貨の山を見つけたとき、彼は信じられないような自分の幸運に目がくらくらとして、また跳び上がらんばかりだった。
旅人は素早く辺りをぐるりと見回し、彼の「新たに見つけた幸運」を取り上げ馬まで走り、今来た道を急ぎ戻って行った。これだけの銀貨があれば、今まで彼が欲しいと思ったものは何でも手に入れることができた。この金を手に入れた今となっては、はるばるやってきてあと少しでたどり着くとはいえ、あんな小さな村まで行って新しい商売のネタを探すことなど、もはやなんの意味もないことなのだから・・・。
完
2002年11月17日 |