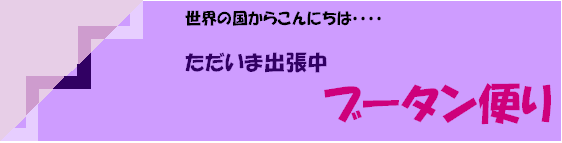
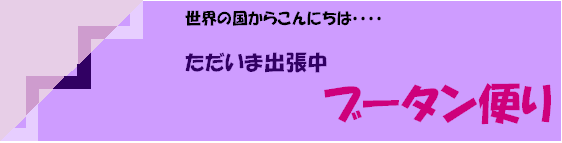
| 31.幸運のお守り(前編)
「テンジン、そんなところで一人、いったい何をしてるんだい?」 背の高いその女は優しい声で、ドルマの家の外の岩の裂け目を鋭い棒でほじくっていた小さな少年に、覆い被さるようにして話しかけた。 「遊んでるのさ」 そう応えると、4才になるその少年は女を一瞥もすることなく穴を掘り続けた。 女は辺りを見回して誰もいないことを確かめると、懐から金色のリンゴを取り出しテンジン少年にさしだした。 「坊や、これをお食べ、美味しいよ」 少年は無造作にそのリンゴを取ると、その場で食べるのが恥ずかしかったのか自分のゴの懐にそのリンゴをしまい込んだ。 「どうしたんだい、テンジン」 女は声を荒げた。 「いま、ここでお食べな。でないと、ほかの子供に取られちゃうだろ?」 そう言われて少年は素直に懐からリンゴを取り出し、両手にしっかり抱えてガブリとかじりついた。 「なんていい子なんだ」 女は薄黒く厚ぼったいその唇の端にずるかしこい笑みを見せながら言った。 女は小さな子供達に彼らの好物を与えることに執着していた。いつも家を出るときには、そんな「すてきな何か」を持って出かけるのだった。 女はふたたび辺りを見回した。誰もいなかった。 「さぁ、誰かが来る前に、ぜんぶ食べておしまい」 そして、どん欲に口いっぱいにリンゴをむさぼり食べる少年の耳元に唇を近づけ、 「いいかい、誰にも私がおまえにリンゴをあげたことを言っちゃだめだよ。それは、最後のリンゴなんだからね。ほかの子供達に『ボクにも頂戴!』、って追っかけ回されるのかなわないからねぇ。わかるだろ?」 さらに、 「もし、おまえが黙っていたら、今度は美味しい桃をあげるからね」 と言って女は少年の気を引いた。 「誰にも言わないよ」 と、女の低い声をマネするかのように、テンジン少年はさらに低い声でささやいた。 「おかあさんにだって言わないさ!」 「本当にいい子だよ、おまえは・・・」 そう言い残して女は立ち去った。 ラモは、その日遅く幸せな気分で家に戻った。彼女にはもう恐れるものはなかった、少なくともしばらくの間は・・。もし村の呪術師さえ彼女のじゃまをしなければ、あの4才のテンジン少年が彼女の命を救ってくれるだろうから。 ラモは、前回彼女が子供に食べ物をあげようとしたときに、呪術師が彼女のじゃまをしたことを思い出していた。そして朝でかける前にかご一杯作ってあった砕いたトウモロコシのバター炒めを取り出した。それからかまどの前にすわって スジャ(塩入りバター茶)の準備を始めた。スジャに使うお茶が沸く少し前に彼女は大きな木窓に歩み寄り、窓の外をぐるりと見回した。 「母さん、母さん、お茶が入ったわよ」 ラモは、母親が土で汚れた手を洗い、お茶の前に座るまでの間にお茶が冷めてしまわないようにと、少し早めに母親を呼んだ。 「はい、はい。今行くよ」 午後のそよ風にたなびく背の高いトウモロコシ畑のざわめきのなかから、母親の声がかすかに聞こえた。 母親のためにお茶を温めなおす間に、ラモはいかに彼女たちの家がまったくもってぽっつんと、そして穏やかな平和のなかにあるかを改めて感じていた。彼女の家は森のはしっこに ひっそりと建っていて、しかも周囲の村の中間地点にあってそれらの村のどれもが全く見えない位置にあった。 ラモは16年前のことを思い出していた。 おばあさんは彼女に、「100年以上も前に、祖先が『村人の噂話』のために、どうやって村を追われたか」、を話して聞かせたのだ。「村人の噂話」がもとで、彼女の祖先の「宮殿のような」立派な家は焼かれ、その家の場所に戻ることを禁じられた祖先は、村はずれの今の場所に掘っ建て小屋を建てたのだという。その後、祖先は家を建て直して今に至ったのだ。 彼女は、この家で3人以上で食事をした記憶がなかった。彼女のひいおばあさんの時代から、村人は、男も女も子供でさえ一家と接触することを避けてきたという。だから、毎年どこの村のどこの家庭でも行う、それは華麗で荘厳な一家の守護神を祭る儀式にも、彼女たちの家族は一度たりとも招かれたことはなかったのだ。また、彼女の家に来てくれるお坊さんなんて一人もいない から、おばあさんは自分たちの家の儀式をすることすらやめてしまったという。 「こんな思いをするのはもうたくさんだよ」 最後に、お坊さんに彼女の家の儀式を行うことを断られたとき、おばあさんは怒りにふるえてこう言った。 「うちの守護神ペルデン・ラモ様をお祀りする儀式にどのお坊さんも来てくれないということが、もしペルデン・ラモ様ご自身の意志のなせるわざならそれでもいいさ。少なくとも私が生きている限り、金輪際、この家で儀式をやることはないさ ・・・」 それはラモが生まれるずっと前のことだった。だから、彼女は一度たりとも儀式の歓びを経験したことはないし、そんな冷たい仕打ちがなくなるだろうことも期待なんかしていなかった。疲れ果てて喉を渇かせた旅人でさえ、彼女の家の前をこそこそとすり抜けていった。家には大きな かめに入った冷たいバターミルクがたっぷりとあり、冬でさえも新鮮でおいしいキュウリがあったのにもかかわらず・・。 いままでにたった一人、彼女の家に立ち寄ったのは村の呪術師だった。彼は家族が出してくれた食べ物や飲み物を口にして心から満足した。でも、その呪術師が臆することなくその家で出されたものを飲食したのには、それなりの訳があったのだ。 彼は近隣の5つの村でたったひとり、呪いに満ちた食べ物の呪いを解くための「女言葉の呪文」を体得した呪術師だった。もっとも、家族はそんなことは気にしていなかったようだが・・。 一方、ほかの村人達はラモの家族が触れたどんな食べ物も恐れて口にはしなかったし、触れられることさえも恐れていた。そして、そうこうするうちに一家は「呪われた一家」とされ、「毒もり一家」と呼ばれるようになったのである。
ちょうどそのとき、沸騰したお茶が吹きこぼれてかまどの火を消し、灰が飛び散った。 ラモはうたた寝からとび起きた。彼女はあわてて半分燃え尽きた薪を取り出し、沸騰してしまったお茶を冷まそうとした。 彼女は台所から古びて柄のとれた木製のバター茶器をとりだし、フィルターを置き、ポットのお茶を注ぎ込んだ。 そして、かまどの近くのすすだらけの棚から強い臭いのバターを取り出し、木さじでお茶のなかに入れた。 さじに付いたバターをこそぎ落とすようにお茶をかき混ぜ、別の壺から同じ木さじで塩をすくってお茶の中に入れ、そしてまた、木さじを洗うようにかき混ぜた。そうやってバター茶を作っている間、彼女は再び遠い記憶をたどっていた。
ラモがチェリンに出会ったのは、彼女がまだ17才の時だった。 チェリンは強引にラモの処女を奪いセルドンを妊娠させたが、結婚することはかたくなに拒否したのだった。 「ラモ、オレは心からおまえのことを愛しているし、おまえが同じようにオレのことを愛しているのは知っている。でも、オレはおまえとは結婚できないんだよ。たとえおまえがオレの子供をはらんでいてもな・・」 チェリンはラモにそう宣言した。 「でも、なぜ?」 ラモは彼にしがみついて泣き叫んだ。 「なぜならな・・・、なぜならばおまえが『毒もり一家』の娘だからだよ・・」 チェリンは悲しげに応え、彼女と目を合わせないようにそっと顔をそむけた。 「どんなことがあっても、オレの家族はおまえを義理の娘として受け入れてはくれないよ」 「でも、そんなのうそっぱちよ。私のおかあさんはあんたが言うような人間じゃないわ! あなただって、そんなの下劣な噂だってことわかってるでしょ!?」 彼女は、恋人を納得させようと必死に話しかけた。 「頼むからわかってくれ、ラモ。オレは普通のつつましい家庭の生まれなんだ。家族仲良く暮らしていくことだけが生きがいなんだよ。おまえと結婚することでその生きがいを壊したくないんだ。オレがおまえと結婚したら、家族からも友人からも縁を切られるに決まってる。」 チェリンはこの上ない失望感に困惑しきった様子でラモに話しかけた。 しかし、ラモは、あまりの驚きと悲しみに言葉を失い、引き裂かれた心に手を押し当て、口を開けたまま立ちすくんでいた。 すると、とつぜんチェリンは彼女の手を振り払い、彼女を一人残して歩き去っていった。 彼女は彼を引き留める言葉をなんとか見つけだそうとしたが、喉はからからに乾き、暗闇はすっぽりと彼女を包み込み体中の気力を萎えさせていた。ついに彼女は、完璧に飢えてやせ衰えた雌犬が雷に打たれたかのように、埃っぽい地面にへたり込んでしまった。 我に返ったラモは、絶望的な叫びと狂気の笑い声の渦巻く中、母親と祖母のいる「避難所」に向けて家路を急いだ。彼らが、チェリンが言っていることが間違いだと証明してくれることを願いながら・・。 ラモは出くわしたもの何にでも噛みつく狂犬病に罹った犬のような勢いで家に飛び込んで、母親と祖母に何があったかをまくし立てた。 「おちついて、ここに座りなさい。これから、おまえの母親や、私が何年も前から話さなければと思っていたことを話すから・・。」 老女はラモの話を聞いたあと、おだやかに言った。 「どういうことなの、おばあちゃん!」 ラモは老女の顔をにらみつけて言った。すると、そこに母親が歩み寄り、 「おかあさん、もう話さなきゃだめみたいね」 と、さらにラモを困惑させるようなことばを、ご近所への挨拶のようにさりげなく言い放ったのだ。 「そうだねぇ。ラモはすべてを知ってしまったんだから・・・。まだ17才なのに、こんな事になってしまって・・」 老女は、まるで樫の棒で強く殴られたかのように頭をぐるぐると回しながら応えた。
熱いお茶が茶器を抱えていた左腕にかかり、ラモは再び我に返った。 キラの袖で何事もなかったかのように無造作に腕にかかった茶をふき取り、アルミのポットに上手にお茶を移したとき、母親が家の中に入ってきた。 「トウモロコシ畑の豆の雑草取りをしてきたのさ」 老女は言った。 「そろそろ豆の蔓がトウモロコシに巻き始めたよ。今年も良く穫れそうだねぇ。」 老女は鍬の先を台所脇の柱の隙間に架け、ゆっくりとかまどの方に歩み寄った。そしてかまどの火の脇に座り、シワくれた手をかざして乾かし始めた。ラモは注意深くポットから スジャ(塩入バター茶)を左手の手のひらに少し注ぎ、塩加減の味見をした。塩加減に満足した彼女は大きなカップにとりわけて、母親に差し出すとこう言った。 「シャムリンに行ってきたわ」 「知ってるよ。いいことあったのかい?」 と老女は訊いた。 「そうね・・」とラモは応え、さらにためらいながらも話を続けた。 「ドルマの息子テンジンにうまくリンゴを食べさせたわ」 「それはいい」、と老女は素早く反応した。 「しばらく平穏に暮らせるよ」 ここしばらく、村の誰も彼女達の手から飲み物や食べ物を口にすることがなかったため、仏壇においた銀の椀の中のコインが夜中じゅう「ちりんちりん」と鳴って、毎日夜更けから朝方まで彼女達の眠りを妨げていたのだった。 母娘は、その音の意味する唯一のこと--一刻も早く誰かに毒をもって殺し、呪いを果たさなければ彼ら自身が死ぬ--を良く知っていたのだった。 年老いた母親と言葉を交わすこともなくお茶をすすっている間、ラモは三たび記憶を呼び覚ましていた。 「すべては、おまえのひいひいおばあちゃんにあたるタウモの時代に始まったことなのさ」 祖母カルドゥンモは、チェリンがラモを捨てた夜、ラモに語り始めた。
それはタウモがチベットのラサに旅をしたときのことであった。 タウモは道中のカルチュで、やはり一人で旅をしていたチベット人の青年に出会った。ともにラサを目指していたため、二人は一緒に旅を続けることにした。やがて二人はお互いに惹かれ合うようになった。そして、夜を共にするようになった数日後のある晩、その若い旅人はタウモの腕の中で突然の死を迎え ようとしていた。息を引き取る寸前、彼はタウモに美しい金メッキのされた銀の椀を手渡した。その椀には一杯の銀貨が入っていて、彼はそれが彼女への愛の証だと説明した。そしてその椀が「幸運のお守り」であり、決して手放してはいけないと彼女に話した のだ。 さらに彼は続けた。 「そのお守りを持つ者は、椀のなかのコイン1枚たりとも使ったり人にあげたりしてはいけないんだ。もし、1枚でも使ったり他人にあげたりすれば、決して解けることのない呪いがかけられる。そしてその呪いとは・・・」 そう言いかけて、彼はその場で息絶えてしまった。 ラサから戻って9ヶ月後、タウモは美しい娘のドルカルを産んだ。すなわちラモの祖母カルドゥンモの母親である。 タウモはその後一生独身を貫き、ドルカルが家の商売を手伝う事ができるようになるまで、毎年ラサへの旅を続けていた。 そのころには、タウモは県で一番裕福な女性となっていた。 そしてそれまでの間、タウモはずっと「お守りの椀」を儀式に使う布に包んで仏壇の奥に隠しておいた。お守りのことは誰にも話はしなかった。誰かがそのお守りを彼女から奪うのではないか、とそのことだけが気がかりだったのだ。 ある年、タウモは1年にわたる巡礼の旅に出かけた。タシヤンツェのチョルテン・コラ、ブムタンのジャンペ・ラカン、クルジ・ラカン、タムシン・ラカン、メバルチョ・ラカン、パロのタクツァン、ブムダ、キチュ・ラカン、ドゥンチ・ラカン、ジャ・カルポ、そしてインドに渡り、ブッタガヤ、ベナレスまで達した。 母親が巡礼中のある日、ドルカルは仏壇の掃除をしていた際に偶然「お守りの椀」を見つけた。そして数日後、ドルカルはラサにむけて旅立った。その椀から取った4枚のコインを持って ・・・。 ある日、タウモはベナレスに滞在し、ある高僧を訪ね祝祷を受けていた。 その祝祷が終わったとき、高僧は突然タウモに、 「あなたは、あの椀のことを娘に話しましたね」、と言い、彼女を驚かせた。 (千里眼だ!) その頃ラサでは、ドルカルがチベット人の宝石商から大きなトルコ石の二重の首飾りを手にしていた。あの銀貨とひき替えに・・。 そしてまさにその夜、ドルカルの夢の中に、ひとりの寂しげな顔をしたチベット人の青年が現れた。 「ドルカルよ、あなたはあの椀からコインを持ち出す前に、お母さんに相談すべきだった。コインを使ってしまったいま、呪いはあなたとあなたの母親、そしてあなた達の子孫末代までも解かれることなく祟るでしょう」 夢の中のその青年は声を限りに泣き始めたのだった。青年が声を殺すように土埃の中に顔を押しつけなおも泣き続け倒れ込む時、ドルカルはびっしょりと冷や汗をかき、あえぎながら眠りから覚めた。彼女が投宿したラサの家は満 天の星に照らされ、不気味な犬の鳴き声と狼の遠吠えに包まれていた。ヤクの毛の入った彼女の布団はラサの凍てつく夜にもかかわらず冷や汗でびっしょりと濡れていた。 そしてそのとき、ヤクの油のランプを持った家主が彼女の部屋に入ってきて、彼女に向かってチベット語でこうつぶやいたのだ。 「Dendray gi tendrel nyenpa!」(この魔女め!) ドルカルは心臓が止まりそうになった。 彼女が起きていることに気づいた家主は、びっしょりと汗をかいている彼女に気づき、 「だいじょうぶかい、ブータンの娘さん」 と声をかけた。 次の日朝早く、とりつかれた女、ドルカルはラサの町中を回って宝石商を探した。しかし、誰も彼女が言うような宝石商を見た者はいなかった。彼の宝石商はラサの薄い空気のなかに消えてしまったかのようであった。彼女の首にかけてあったはずのトルコ石の首飾りとともに、忽然と・・・。
その運命の日、悪夢の夜を過ごしていたのはドルカルだけではなかった。 ドルカルが冷や汗にまみれてラサの夜を凍えながらベッドに座っていたそのときに、彼女の村でも、犬という犬すべてが薄気味悪いうなり声と遠吠えで村人を起こして眠らせなかった のだ。犬たちは、まるで戦争でもしているかのように、あるいは彼らの親戚の狼とともに、彼らすべてを陥れようとする死への使いに対して恐れをぶつけるように、きちがいじみた振る舞いをしていた。 そしてある村人は、一羽のフクロウが見えない恐怖に取り憑かれ、村のすべての男、女そして子供達を起こすまで、「ほうー、ほうー」と泣き叫びながらドルカルの家の周りをぐるぐると飛んでいるのを見た。さらに恐ろしいことに、翌朝までにすべての家で、一羽のにわとり、一頭の馬、一頭の雌牛、子牛そして雄牛、一頭のロバと豚が死んだのである。そう、ドルカルの家を除くすべての家で・・。その日、村の長老達は悪魔の呪いについて村の占星術師に相談した。そして恐ろしいことに占星術師は、「村の誰かに呪いがかけられ、その呪いはその村だけでなく、近くの村でも多くの生命を奪うだろう」、と予言したのである。
ドルカルは、家に戻った後、4枚のコインを自分のコインで補おうとした。しかし、驚くべきことにその椀はすでに縁までコインがびっしり詰まっていたのである。もちろん、ドルカルも母親も、椀の中のコインの数を確かめたことなどなかったし、ラサでドルカルが使った4枚のコインが元に戻っているなどと確かめる術もなかった。しかし、ドルカルも母親も、そうであろうことを信じていた。 さらに、奇妙なことに、ドルカルがコインを足そうとしたまさにその夜に、彼の宝石商が彼女の夢の中に現れた。宝石商はしばらくドルカルの顔をじっと見つめていたが、突然その長い茶色い指で彼女を指し、真夜中、彼女が叫び声をあげて目を覚ますまで、けたたましく笑い続けた のだ。 タウモは娘ドルカルから、彼女がラサで4枚のコインを使ってから起こったことすべてを聞いた後、2時間歩いてクリチュ川まで行き、その銀の椀を川の真ん中めがけて投げ捨てた。ところが驚いたことに、その椀は沈むどころか、羽毛のようにぷかぷかと浮いていた。タウモは夢でも見ているのではないかと何度も目をこすった。しかしながら、彼女の期待とは裏腹に、その椀はクリチュ川の荒れ狂う流れの上を、彼女のいる岸に向かってスイスイと進み、まるで足が生えているかのように乾いた砂の上に這い上がってきたのだ。いや、足ではなく羽根が生えたかのように・・・。砂の上には何の跡も残っていなかった。そして椀は濡れることなく、炎のように乾ききっていた。 タウモは椀に石をくくりつけた。そしてその椀を川に投げ込むと、沈むかどうか一瞥も確かめることもせず、彼女は川辺を恐ろしい勢いで離れ、家路を急いだのであった。 しかし、家にたどり着き台所のかまどの脇にへたり込んだとき、彼女はカレー用の土鍋の脇に、あのクリチュ川に捨てたはずの椀を見つけたのだ。彼女は何度もその椀を燃やそうとした。しかし、真っ白に焼けた炭の山の中に半日置いたあとでも、その椀は1月の霜のように冷たかった のだ。 それ以来ずっと、その椀は彼女の家に置かれたままになっている・・・。呪いとともに。
「ごめんよ、ラモ。でもね、これが本当のことなんだよ。 そして、私たちは、あの呪いを受け入れるしかないんだよ」 長い話のあと、カルドゥンモは孫娘のラモに向かって寂しそうに呟いた。 中編につづく・・・。2002年11月3日 |