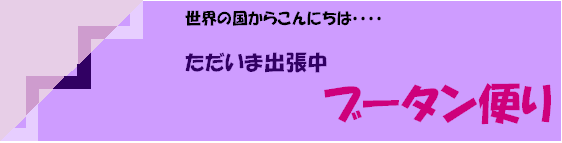
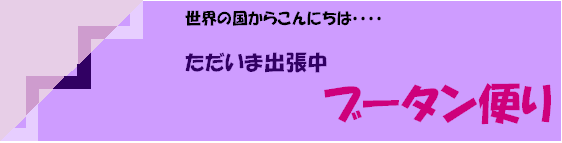
| 31.幸運のお守り(中編)
「でも、どうしてみんな私たちを『毒もり一家』って呼ぶの?」 ラモは泣きながら訊いた。 「それはね、わしらへの呪いが毒になって顕れるからなんだよ。 わしらの手から渡された食べ物や飲み物を口にした人にはみんな、その呪いの毒が回るんだよ。だから、みんな わしらのことを『毒もり一家』って呼ぶのさ。」 ラモのおばあさんはそう説明した。 「なんてことなの! でも、もし私たちが出した食べ物すべてに毒が入ってしまうというなら、他人に飲み物や食べ物なんか一切あげなければいいじゃないの。 それに、呪いの毒は私たちのこどもとか、家族にだって向けられるんじゃないの? そして、家族に食べ物や飲み物を与えなかったとしても、結局は自分自身に呪いがかけられ、死んでしまうことになるわ 。だけど、それでも、自分の家族や子供を殺してしまうよりはずっとましだわ。」 ラモは、激しく祖母にくってかかった。 「 もし、どんなことをしたってその呪いが解けないってわかったら、自分を殺したって仕方ないじゃないか。他人に呪いの毒を与え続ける限り自分の子供に危害がおよぶ事がないとわかったら、なんで子供を殺すようなまねができるんだい」 老婆は疲れ切ったヨガ行者のように言い切った。 「でも、どうやってその毒が食べ物に入るの? その毒っていったいなんなの?」 「それはね、物じゃないんだよ。見ることはできないし、においを嗅ぐこともできない。触れることもできないし、聞くこともできないのさ。ただの呪いなんだよ。一旦取り憑かれたらずっとおまえにつきまとうのさ。」 「わからないわ。どうして自分が呪いにかかったってわかるの?」 「自分が与えた飲み物や食べ物を口にした人が次から次へと死んでいくからわかるのさ・・・」。 カルドゥンモは悲しげに答えた。 「でも、人はどんなことでも死ぬじゃない。どうして私たちの毒のせいだってわかるの?」 ラモは納得しなかった。 「人はね、わしらの呪いの毒によるような死に方は決してしないのさ。 それにね、わしらの毒で苦しんでいる者には一切の薬が効かないんだよ。それどころか、薬は毒の効果をもっと強くしてしまうのさ。 これまでにたった一人、 わしらからの食べ物を口にして死ななかったのは、村の呪術師のナペイだけさ。あいつはわしらの呪いの毒を解く呪文を知っているんだよ。だけどね、あいつだって最近は危ないもんさ。そのうち、あいつもあの難しい呪文を忘れ、 わしらの呪いの毒の餌食になるさ。」 「おばあちゃん、まさか・・・」 ラモは悲鳴ともつかない声でいった。 「そうだよ。あいつさえ死ねば、わしらの命は永遠なのさ」。 「どういう意味?」 「あいつがわしらの毒から人を救えば救うほど、わしらの家族の身に危険が迫ってくる。人を殺さないと毒が自分や家族にふりかかってくるんだよ。この呪いはね、そうやって人に呪いの毒を与え続けないといけないものなのさ。私のおばあさんのタウモはね、そりゃぁ信心深い女だったんだ。でもね、タウモばあさんに呪いがかけられた後、たくさんの村人がおばあさんからもらった食べ物を口にして死んだんだよ。わずか1年半の間に、村人はおばあさんのことを、「7人もの村人を殺した毒もり」と呼ぶようになったんだよ。そしてね、おばあさんは、毒が呪いの正体だと気がついてからは誰にも食べ物や飲み物を出すことはやめたのさ。でもね、結局はそのことがおばあさん自身の命を奪うことになったのさ。おばあさんはね、呪いの毒で死んだ村人と全く同じ症状にかかって死んだんだよ。そして、村人はみんな、おばあさんが毒をもり間違えて自分が死んだと思ったのさ。 それからね、私の父親は、母のドルカルが他人に食べ物をあげるのをやめた後、同じように死んでしまったんだよ。」 「呪いから逃れる方法はないの?」 ラモは訊いた。 「誰も知らないんだよ。だけど、どうしておまえは、まず呪いから抜け出すことを考えるんだい?」 老婆は続けた。 「呪いはわしらの家族を守り、富と力をもたらすんだよ。村人はわしらを避けるかもしれないけれど、だれもわしらに危害を加えようと近づいてこないし、自分自身が近づかなくても、自分の子供や親戚が わしらの毒の犠牲になるかもしれないとビクビクしているのさ。」 「でも、チェリンは私を捨てたのよ!」 ラモは当惑して言った。 しかし、ラモの言葉など全く耳に入っていないかのように、老婆は続けた。 「たとえ番兵なしに玄関の扉を開けっ放しにしてたって、呪いにかかることを恐れてだれもわしらの家から物を盗ろうとしたりしないしね。」 そして、大きなため息のあと深く息を吸い込んで、老婆は大きな声で言った。 「そうかい、そうだったのかい」 老婆は不意に落ち込んだ居眠りから無理やり目を覚ますかのように、含み笑いをしながら首を振って続けた。 「それならおまえも、誰も私たちの家族になろうなんて者がいやしないってことがわかったろう?」、 老婆はラモをちらりと見て不気味に笑った。ラモは、家中に響く老婆のぞっとするような笑い声に身の毛がよだつのを感じた。 「おばあちゃん・・・」 ふるえる唇で呟くようにいったまま、大きな目を見開いてラモは老婆をじっと見ていた。しばらくたってから、老婆は言った。 「ラモ、いいかい。チェリンがおまえにしたことは、ちっとも驚くような事じゃないんだよ。これはよくあることなんだよ。すくなくとも、我が家の女にはね・・」 「でも・・・。」、ラモは何かを言いたかったが、言葉が出てこなかった。 「わしも、そしておまえの母親も同じ目にあったんだよ。わかるかい?」 老婆はラモを慰めるように言った。そしてラモは次の言葉を聞いて仰天した。 「わしらの相手の男がね、他の女との間に授かった子供だって生き延びることはできないんだよ。そして、その相手の女が死んでやもめになってもね、だれもその男とは結婚しないのさ、ははははは」 老婆は再び、抑えることがでない笑いに涙まで流しながら腹を抱えて笑い続けた。 「でも、おばあちゃん。私のおなかにはチェリンの子供がいるのよ。」、ラモは不満そうに言った。 「私たちだってそうだったのよ・・・」 長い沈黙の時間を取り戻すかのように母親が会話に入ってきた。 「心配するんじゃない。少なくともおまえが年老いたときにそばにいてくれる娘ができるんだ。知ってのとおり、私たちはみな娘を産んだんだよ、呪いを引き継いだね。」 その後、3人の女は夜を徹して話し続けた。そして最後に、ラモはどうするべきかを悟ったのだ。
そしてその後15年以上に亘ってラモは、チェリンが妻との間に作ったすべての子供と、周囲の村の若いカップルに呪いをかけ続けたのだった。何人かは、村の呪術師ナペイの息子にして、ナペイから多くの呪術を習得したペマによって救われたが、そんな幸運を手にしたのは、ほんのわずかな者にすぎなかった。ペマ自身、ラモと母親に呪いの毒を与えられた2回とも、父親に救われている。
ところが、ナペイはある日、近くの村でお祈りをしたあと一人でラモの家にやって来て酒を飲み、確かに老婆が言ったように、呪いを解く聖なる呪文を唱えるのを忘れ、そのままラモの母親と一夜をともにしてしまったのだ。
そしてまた、ナペイの息子ペマがラモに惹かれていて、まもなく父親と同じ過ちを犯すだろうということを、ラモはなぜか感じとっていた。そしてラモはチェリンの妻も殺さねばならなかった。チェリンが、ラモの父親や祖父と同じように、一生やもめで暮らしていくために。自分が幸せな暮らしを送ることができないなら、どうしてチェリンの妻が幸せに暮らしていいだろうか。
ある日チェリンは4人の男達と2日間泊まりがけで隣家の薪集めのために山に入っていた。数え切れないくらいの薪を背負って2日間歩き続け、村に戻ってきたとき男達は疲れ切っていた。隣家の女主人はなにが男達の体の痛みを和らげるかを十分よく知っていた。女主人は、4ヶ月以上も発酵させたあと熟成した、鼻にツンとくるような強い酒を男達に振る舞った。女主人は5杯目の酒を注ぎながら、さらに酒を勧めた。
「もっと飲んでくださいね。この酒は8ヶ月間以上も熟成させたものなんですよ。」
そして注ぐたびに女主人の言う、その酒の熟成期間は長くなっていった。
ちょうど女主人が夕食を振る舞っていたとき、入り口から息を切らしたチェリンの妻ドルマが飛び込んできた。
「チェリン、早く帰ってきて! テンジンの様子がおかしいのよ、早く!」
たった一人生き残っている4才になる息子テンジンは、5日前から腹痛を訴えていた。そしてこの2日間は寝込んでいたのだった。はじめはチェリンもドルマも、息子の腹痛が天候かちょっとした食べ物のせいで、すぐに治るだろうと考えていた。しかし、下痢が止まらないことになにか最悪の事態が起きていることを疑い始めたドルマは、呪術師ペマを呼びに人を遣り、ペマが来るのをひたすら待ち続けていた。 しかし不幸なことにとのときペマは遠くの村まで出かけていたのだ。
チェリンが息を切らして家にたどり着いたとき、彼は牛車に轢かれた猫のようにベッドの上でもんどりうってのたうち苦しむ息子の姿に愕然とした。妻が半狂乱になって息子にとりついた悪魔の魂を追い払おうと泣きわめいているとき、チェリンは息子の体が熱っぽい赤色から、腐ったような青っぽい緑色に変わっていくのに気が付いていた。そして、まもなくその青っぽい緑の斑点が体中を覆い尽くし息子が最後の息を吐いたとき、まさにチェリンの最悪の予感は的中したのだった。彼の昔の恋人が、またもや彼の息子の命を奪ったのだ。
チェリンは息子を膝に乗せたまま、瞑想でもしているかのように座ったままじっと動かなかった。彼は声を限りに泣き叫び両方の拳で自分の胸をたたき続ける妻をじっと見つめていた。 次の瞬間、チェリンは頭を膝の上の息子の方に落としたかと思うと、そのままドスンと突っ伏してしまった。ドルマは息子の上に覆いかぶさるようにして身動き一つしない夫に気がつき、夫の肩をゆすり、抱きかかえた。
「チェリン、起きて。テンジンは逝ってしまったのよ。お葬式の用意をしなければならないわ。」
絶望にすすり泣きながら、妻は夫を慰めるように話しかけた。 しかし、チェリンは身動き一つだにしなかった。ドルマがさらに強く夫の肩を揺すったとき、その体は床にごろんと仰向けになり、子供の遺骸のそばに息もなく横たわるだけだった。チェリンもまた死んだ。 彼は4人目のそして最後の子供の死に直面し、そのショックに耐えることができなかったのだ。
ドルマは、悲痛な叫びをあげ、もう何も感じないであろう夫の肩を抱きおこし、前に後ろにとあらんばかりの力でその体をゆさぶった。そしてすぐに、彼女は自分をひとりにしないでくれと拝むように泣き叫び、一方ではこの悲劇に直面する自分一人を残して逝ってしまった彼を 責めた。
ドルマの哀れな叫び声を耳にした10人以上の近所の人々が彼女の家にかけつけたとき、ドルマの家の中は、まるで苛酷な戦闘が繰り広げられたあとの戦場のようであった。けが人はなく、2人の戦死者の遺骸を残すのみの・・。村人はテンジンとドルマへの悲嘆の思いとともにチェリンの突然の死に大きな衝撃を受けていた。わずか3人ばかりの長老がドルマを必死で慰めただけで、あとの村人は悲しみにくれ泣き叫び、すすり泣き、絶望のどん底でその場に立ちつくすだけだった。3人の長老がその悲惨な場所からドルマを引き離そうとしたが、その未亡人は、決して動くことのない夫の亡骸にしがみついて離れようとしなかった。 そして、突然、彼女もまたバッタリと突っ伏して動かなくなった。
次の日、村人のほとんどが、そして近くの村からも多くの人が、木綿の布に包まれた3体の遺骸を荼毘に付すため、火葬場への長い葬列をなしていた。そして遠く離れたところから、ラモはその葬列をながめていた。目に一杯の涙をためて。ラモは、愛しいチェリンにこんな事が起きるなど全く望んでいなかった。彼女は復讐の思いをとげたかったが、それはチェリンの死ではなかった。ラモはあれ以来ずっとチェリンのことを愛し続けていたのだから。
15才のセルドンは村で一番可愛らしい10代となっていた。村のどこに行っても、同世代の少年はおろか、ずっと年下の男の子や、既婚、独身を問わずあらゆる年代の男達、そして女性達もが彼女に目を奪われていた。セルドンは雌ライオンのようにゆったりと歩き、ナイチンゲールのような声で語りかけた。彼女はすべての好色な男達の憧れの的であり、恋する少年すべての天使であり、すべての親達が夢見るような愛らしい子供であり、すべての少女の「かなえられない夢」だった。彼女は養父母とその子供達にもかわいがられ、そして近所の人々にもほれぼれと眺められていた。そう、彼女は幸せに生きるためのすべてを身につけていたのだ。いつの日か遠い国から王子様が村にやってきて彼女を馬に乗せ宮殿に連れ帰り、その後一生二人で幸せに暮らすことを彼女が夢見ても何もおかしくはなかった。
ところが、彼女の養母とその子供達以外はみな、決して彼女に近づこうとしなかった。彼女の実の母親が誰であるかを知っていたから・・。 彼女の持って生まれた美しさをもってしても、実母が先祖から引き継いだ呪いの影から彼女を守ることはできなかったのだ。彼女が呪いを引き継いだという確かな証はないにしても、彼女が呪いを引き継ぐ運命を背負った女性であることを、誰も忘れはしなかった。彼女が子供の頃、遊び仲間の一人か二人かは必ず彼女を「毒もりの娘」と呼んだ。彼女は反論も自己弁護もできず、たった一人逃げ帰っては涙が枯れるまで泣き続けた。そしてそれ以上泣くことができなくなってから養父母のところに駆け寄っては、どうしたらその耐え難い誹謗中傷から逃れられるかを尋ねた。
最初のころは養父母も、セルドンを「毒もりの娘」と揶揄したおしゃべりな子供達に平手打ちをくらわせたり、そうするぞと見せかけて娘を守ろうとしたが、そのうちに彼らもそうすることに疲れたのか、「時間が経てばすべてが解決するから、おまえも我慢しなきゃ」、とセルドンに言い聞かせるようになっていった。そして彼女は言われるがままにずっと耐え続けてきたのだった。
セルドンの実母ラモは決してセルドンに会いにくることはなかったし、セルドンも会いに行くことを許されていなかった。もちろん、子供の頃はそんなことはあまり大したことではなかった。しかし、成長するにつれて、彼女は「両親としている二人」が実の両親ではないことに気がついていたのだ。そして、ときに彼女の頭のなかに、「実母に会いたい」という思いがよぎり、それは次第に「どうしても実母に会いたい」との衝動に変わっていった。
彼女が最初で最後、ラモを人混みで見かけたのは、別の村で行われた祭典の会場で、彼女が12才の時だった。彼女はそこで背の高い女性が自分を何度も見つめているのに気がついたが、そのたびに目をそらしていた。そしてそのとき、隣に座った老女が、その背の高い女性 こそが彼女の実母であることを教えたのだった。 反対側に座っていた養父母がその言葉を耳にして、「余計なことを言うな」、とその老女をたしなめたとき、セルドンは人混みの中で実母が立っていたはずの場所を見やっていたが、その背の高い女は足早に人混みの中に消えようとしていた。セルドンは母親の顔を覚えていたが、養父母に厳しく禁じられ、 その後母親を訪ねようとすることは決してしなかった。
セルドンが15才になったとき、養父母はほかの子供達を部屋の外に出しドアに鍵をかけると、セルドンに彼らが知っている限りの彼女の先祖のことを話して聞かせた。そしてそのことで、彼女はそれまでのように実母を恋しがることもなくなったのだが・・・。
実は、セルドンの養父のデンドゥップは、彼女の実母ラモの唯一生き残った腹違いの兄弟だった。ラモがセルドンを産む少し前に、彼女は娘が呪いを受け継ぐかもしれないことを知っていた。そこでラモはデンドゥップに 会いに行き、密かに「秘密の計画の実行」を依頼したのだ。彼女はデンドゥップにお腹の子供がすでに呪いを引き継いでいるだろうことを告げ、セルドンをデンドゥップ夫妻の養女にすることを懇願したのだ。 彼女は決して生まれてきた子供に近づかないこと、触れもしないことを約束した。そして生きている限り彼の村に近づかないことを約束した。さらに、ラモはデンドゥップに、セルドンが適齢期になるまで、決して実母が誰であるのか、そしてその家族にまつわる忌まわしい歴史について話さないことを約束させた。
「私の母親もおばあさんも、私が自分の判断で人生を変えるには遅すぎる段階まで、呪いの秘密を教えてくれなかった。だから、私はせめて自分の娘が、適齢期になるまでは、この忌まわしい呪いの恐怖におびえることなく暮らしてほしいと、そしてそのために、呪われた私たちの家ではないところで育ってほしいと思っているの。私は彼女から、殺人者となるか命を与える者となるかの選択肢のどちらをとるか、それを自分自身で判断する権利を奪いたくないの。そして私が彼女にその権利を与えるためにできる唯一のことは、呪いが彼女に取り憑く前に、彼女に自分自身で選択する機会を与えてあげることなのよ。私や私の母親以外の人に育てられ、私や私の家族から一切ものを与えられることがなければ、呪いは彼女に取り憑くことはないと願っているの。」
ラモは、デンドゥップに、生まれる娘を里子に出す理由を訊かれたときにそう答えたのだった。
「ね、おまえ以外の誰がいるって言うの?、ね、そうでしょ。お願いよ、後生だから私の娘をこの呪縛から救ってあげて。」 ラモは顔を覆い泣きながら弟に懇願した。 「どうか泣くのはやめて、姉さん。安心して家に帰って。姉さんが望むようにするから・・・。でも、姉さんも約束はしっかり守ってくれよ」、とデンドゥップは答えた。 「もちろんよ、わかってるわ。ただ、もう一つだけお願い。私だって先祖が長年かけて必死に積み上げてきた立派な遺産を自分の手で彼女から奪いたくはないの。だからお願い。彼女が十分理解できる年頃になったら、すべてを彼女に話して、自分自身で正しい判断をさせてあげて。そして、彼女が自分の意志でその呪いと彼女が引き継いだものすべてから決別することを決めたなら、私は幸せな思いで死ねるわ。でも、もし彼女がうちに来て彼女の受け継 ぐべき遺産を要求することを決心したら、私は悲嘆に暮れるでしょうね。」、ラモは言った。 「姉さんのつらい思いはよくわかるよ。妻も私も姉さんや子供をがっかりさせたりしないさ」 デンドゥップは、同情の想いから自分の心がフライパンの上のひとかたまりのバターのように溶けていくのを感じながら、止めることもできず泣き続ける腹違いの姉に約束した。 「自分たちの子供のようにあなたの子供を育てていくわ、姉さん」、とデンドゥップの妻もラモを安心させようと語りかけた。 ラモが陣痛を感じ始めたとき、彼女は牛飼いを送りデンドゥップとその妻に出産が近いことを知らせた。セルドンは母親の家からかなり離れた牛舎で、デンドゥップ夫妻が着くとまもなく生まれた。デンドゥップの妻が赤ん坊を抱き上げたとき、ラモはすぐにその赤ん坊を連れ去って彼女を一人にしてくれと頼んだ。 生まれて3ヶ月になる自分の赤ん坊を育てていたデンドゥップの妻はセルドンにも同じように母乳を与えた。それ以来セルドンは、彼女の叔父・叔母夫妻に実の子のようにして育てられたの だ。 後編につづく・・・。2002年11月10日 |